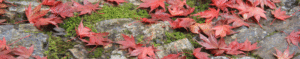この期間私と母は本当にのびのびと過ごした。
父は不幸な子供時代を過ごした人であった。大変な努力家であったが、愛情の欠如した子供時代を過ごした事からくる性格のゆがみは私達には如何ともできなかった。何故に怒るのか分からない点で突然に怒り出し、何日も口を利かないことがよくあった。その性癖はこの母の状況になおさらにひどくなった。母だけが大切にされ、自分はないがしろにされていると全く不機嫌だった。その父をなだめるために母も私も疲れてしまうことが多かった。
しかしこの時、その父が半年にわたり入院のために家を不在とすることとなった。父の理不尽な小言から離れて私と母は自由に時間を過ごすことができた。夕食の代わりにお好み焼きを食べにでかけたり、私が仕事から帰ると遅いお茶を楽しみながらいろいろと会話を楽しんだりした。母の発病が確認された時点で父が閉ざしたクリーニング業を母は小規模に再開したり、母が好きだった車の運転も体調を考えながら少しずつ取り組んだりし始めた。再び車を運転できるようになった母と二人で御坊に墓参り出かけたり、有田にみかんを購入に出かけたりもした。私は母に進められて従妹とともに東京ディズニーランドに一泊で出かけたりもした。その従妹との旅行に母は入院中の助力に対するお礼として従妹に紙包みを渡していたがそれも父がいないからできたことであった。少しずつ母は回復している、と私たちは確信していた。
その次の年の5月の母の日に精度の良い老眼鏡を買ってほしいと私に頼んできた。母が私に何かを買ってほしいと頼むのは非常に珍しいことであったから、私は母に老眼鏡が欲しいと訴える理由を尋ねた。すると目が見えにくいから、と母は説明をした。母親は私とは異なり、近眼矯正のための眼鏡は必要とはしなかった。その為に比較的若い頃より加齢のための老眼鏡を必要とするようになった。老眼はどうせ進むのだからそこに費用をかけるのは意味がないと母は口にしていた。数年前から既に廉価な老眼鏡を使用していた。そのような状況だったのになぜに突然高価な老眼鏡を買ってほしいというのか、私には全く理解できなかった。単純な老眼の進行とは思えなかった。
その状況が非常に不自然に思えた私は直腸がんの手術を施行された外科医定期受診の際にその母の訴えについて報告した。母の『目が見えづらい。』との訴えがなぜ突然に始まったのかと。すぐに主治医は母のために眼科受診を手配し、その日のうちに眼科受診は行われた。院内の他科受診のゆえにそれほどに複雑な手続きではなかった。B5の半分くらいのサイズの紙に外科の主治医はつらつらと何事かをしたためて、眼科受診の手筈は整った。眼科で様々に検査が行われたのち、同じ紙に眼科より外科主治医宛に返事が書かれた。外科に戻る途中何気に目を通すとその紙には動眼神経麻痺と書かれていた。しかし当時医師でもなく、医学に何ら知識を持たなかった私にはその言葉の意味は分からなかった。その紙を手にした外科医は私たちに『目に異常はなかったよ。』と説明した。『いやそんな筈はない、動眼神経麻痺と書かれていたではないか。その言葉の説明はどこに。』心では叫んでいたがその言葉は私の口からは出なかった。叔母の勤務先であること、自分に何も知識のないことが私の口を閉じさせた。その次の受診の折に母はふらつくと今度は外科医に訴えた。耳鼻科受診ということに決まり、同じ手順が行われた。私たちは再び『問題ないよ。』の説明を受けた。最終的に彼が私に言ったのは『うるさいから、ねむらしておけよ。』の言葉で、睡眠剤が処方された。彼は私に対するいたわりを以て口にしたのだと思う。母の診療にいつも付き従う私に対する親しさも込められていたと思う。
しかしながらこの頃から母の具合は日に日に悪くなっていった。一時期は病前のように車を運転できるほどに回復していたのに、目が見えないから危ないから車が運転できないと言い始めた。目が見えない、頭が痛い、気分が悪い、つかれたと臥床することが多くなっていった。車を運転することも完全にやめてしまった。私は母の変化に戸惑い、何とかその変化を説明する手掛かりを得ようとあがいていた。主治医の言う通り、単なる不定主訴とかたづけていいのか、どうか。その手掛かりを得ようとして母に『目が見えないとはどういうことなのか。詳しく状況を言ってほしい。』と尋ねた。すると母は『片目をふさぐでしょう。するとはっきりと見えるの。反対側をあけてもう片方をふさぐでしょう。やはりはっきりと見えるの。でも今度は両方の目でふさぐことなしに見ようとするでしょう。すると壊れた映りの悪いテレビのようにものがだぶってはっきりと見えないの。』この言葉を手掛かりに私は闘病記、素人用の医学書、医師の伝記などを必死に読みふけった。千葉敦子氏の乳がんの闘病記、柳田邦夫氏国立がんセンターにおける医師たちの戦いの記録、等々。コンピューターはまだ発達していず、ようやくにDOS-Vに入った頃の事であった。近い将来インターネットで便利にショッピングなどがすることができるだろうとテレビニュースなどでは言われていたが、インターネットは身近なものとは到底言えなかった。携帯電話はショルダーバッグ状の大きさのものをきわめてわずかの人が利用しているという時代であった。そのような状況の中で情報を引き出そうとすれば、まだ書物に頼るしかなかった。多数買い求めた本は仕事場に置き、他にも情報源を求めて近所の書店に足を運び、何か適切な書籍がないだろうか、とあがいた。結果、ようやくたどり着いた言葉は複視というものであった。片目ずつであれば、問題のない視力が得られる、しかし両眼でものがだぶって見える。母の症状とぴったりと合致するように思われた。一つの手がかりが手に入った。では複視とはどのような状況で起きるのか、次の私の疑問であった。複視の言葉を手掛かりにまた書籍を探そうと読書と書店探索に明け暮れる日々が続いた。
この頃に父が交通事故の外傷治療を終了して退院してきた。結局の所、骨折した骨は医師の望んだ治療方法ではつながらず、最終的に金属プレートで骨折箇所をつなぐ手術となり、手術後経過に問題なく、自宅に帰ってきた。父にとっては待ちに待った退院であっただろうが、私にとっては実の処最悪のタイミングであった。『もっと病院にいてよ!』と心の中で叫んだが、いくら叫んでも状況は背負うべき荷物がひとつ増えたということであった。まだ二輪車に乗ることは不可能であり、父親不在中に母親が細々と再開していた仕事はそのまま父が引き継いだ。そして父の外交訪問の手伝いの車の運転は私がすることとなった。父は交通外傷からほぼ回復したように思われた。気がかりなことは一つ、退院時に整形外科の主治医から言われた『肝機能の数値がおかしいので、奥さんの状況が落ち着いたら検査を受けてくださいね。』の言葉であった。父親の状況をとりあえず放置して、母の状況に対しての心の安定が欲しかった。見つかってきた言葉はやはり動眼神経麻痺、白内障、そしてその当時私の理解できなかった数々の言葉。
その中に脳腫瘍の言葉が含まれていた。私が一番見つけることを恐れていた言葉だった。