京都で勉学に励んで(?)いた頃の話…
父親が亡くなった後、京都と和歌山での二度の葬儀、京都の葬儀社に騙されたというやるせない腹立ち、
疲れと無力感で打ちのめされてしまいました。
もともと学業、父の看病を単身京都で行い、そして必要な収入を得るためのアルバイト
で疲労困憊しておりました。
父の命が限られたものであるということは国立がんセンターより説明されていましたが、
その死のショックは予想を超える大きなものとなりました。
結果、極度の過労のための入院と言うことに帰着しました。
父親に優しくなかったことを申し訳なく感じ自責の念に苛まれ、
医学部を続けることすら無意味に思われ、退学も考えていた時に
入院先の病院の看護師の方から『自分自身の未消化の思いを患者さんに尽くすことで昇華させては…。』
と言われ、医学部を続けることを決心しました。
入学から二年間、馬車馬の如く走り抜けた年月でした。
すべての貯金を父の心の安らぎになるならばと託し、それをないものとして
医学部での学習と生活及び父の医療費のために家庭教師のアルバイトに時間刻みで走り回る日々。
それがすべて終わる…。
もうあくせくする必要もない…。医学部での学習にのみ集中することができる。
こんな家賃の無駄に高い京都の中心にいる必要もない…。
自分自身のために生きよう、快適な環境へと居を移そう…。
それだけでなくどうしても転居しなければならない必要もありました。
どこかで少し書いたストーカー問題です。
見付けた新しい住居は京都市左京区北白川別当町、閑静なお屋敷街の一角にある少し高級な賃貸マンション。
この時代の賃貸に珍しく、インターホンはテレビカメラが付いておりました。
その設備がどうしてもストーカー対策には必要だったのです。
賃貸のマンションは3階から。1階には終夜営業のかなり大きな書店、2階はビルの持ち主たる建設会社のオフィス。
と言うことで建物もかなりしっかりとした作りになっており、外部からの侵入は全く不可能でした。
残念ながらこの居もストーカーに見つけられ、一騒動が勃発するのですがそのことはまた後程…。
この居はロケーション的に非常に良い場所にありました。
南に少し歩くと銀閣寺から哲学の道の北端に入り、南禅寺まで簡単に至ることができました。
逆に北に歩くと、一乗寺。江戸時代の剣豪宮本武蔵が決闘した場所があり、
通り過ぎてさらに歩を進めると詩仙堂、圓光寺、曼殊院、修学院離宮へと至ることができました。
毎日、夕刻になるとどちらかの道を選び、散歩をするのが常でした。
結構な距離を歩くことになるので、帰り路になるとそれぞれの家に灯りが点り、
その灯りのもとに家族団らんが広がっているのだと思うとわずかの期間にそのすべてを失い
天涯孤独となってしまった自身の身が悲しく思われました。
さて、これからお話するのはそんな散歩の途中に出会ったこと。
それはとても寒い冬の日でした。
あまりに寒かったので、通常よりも早い時間に北方向に散歩に出かけました。
曼殊院に至り、雪も降って来たしこの辺りで引き返そうかなと考えていた時、
突然比叡山から大量の猿が降りてきました。
恐ろしい数の猿に驚きあきれて、
立ち尽くしていると曼殊院の客待ちのために待機しているタクシーの運転手さんが声をかけてきました。
『猿と視線を合わせていけないよ。視線を合わせると飛び掛かってくるから非常に危険だよ。』と。
猿たちは曼殊院の前にある大根畑に殺到して行きます。
見ていると大根を畑から引き抜いて両脇に二本の大根を抱えて二足歩行で走っているもの。
(ああこうして二足方向に進化していったのね、とある意味納得しました。)
子猿が母猿の背中に片手で必死にしがみつき、もう一本の手はしっかりと大根を握っています。
瞬く間に大根畑は恐ろしい光景になってしまいました。
お百姓さんは猿に対しては市街地のためにパチンコで応戦するのみ。
彼ら賢くてパチンコの飛距離がそれほど長くないことを見定め、
圏外に素早く移動し、またそこで大根を引き抜く…。
いずれにしても一人のお百姓さんに対処できるはずはなく、
しばらくすると猿は大根を抱えて比叡山に帰って行きました。
カメラを持っていなかったのが返す返すも残念でした。
曼殊院は門跡寺院ですが左京区のかなり山側にあり、
そのあたりはかなり野生動物が出現する地域となっているようです。
最近修学院を訪れた際にも地元の方が『最近は熊の被害も出ているのです。』
とおっしゃていたので、猿などまだ生易しい方なのかもしれません。
でもとても印象的な光景で今も鮮明に記憶に残っています。
曼殊院は格調高い門跡寺院であり、
その雰囲気を今もとどめており、邸内、庭ともに一見の価値はあると思います。
また、これは本来の曼殊院の趣旨とは異なるのかもしれませんが、
近江の商家から託されたという幽霊の絵を展示していることがあります。
これも独特な絵でもし可能であれば、鑑賞されるのも一興かと存じます。


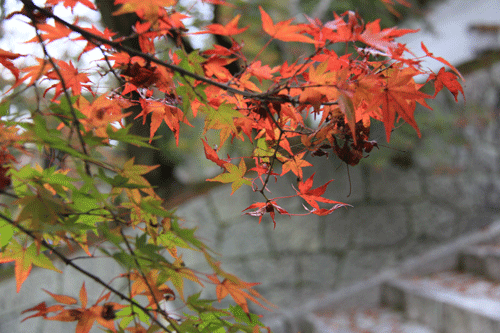


写真は曼殊院だと思います。秋の紅葉の時です。
残念ながら冬の雪の時の写真は見つかりませんでした。


