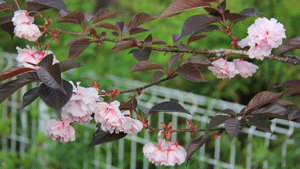時を遡る。
平成元年7月、肺転移及び脳転移が母の病状として明らかになり上昇する脳圧が母の命を奪うであろうことを私達は知らされ、早急に脳内ドレインを入れる手術を行うかどうかの決定を迫られていた。私の決断は脳ドレインの手術を行わない、このまま苦痛だけをできる限り取り除き現在の状況のままに死を迎える、と言うものであった。私の決定に真っ向から反対してきたのはまたしても伯母であった。その当時彼女が私に言ったことはほとんど覚えていない。唯医師の指示に従うのが妥当だ、と言ったであったのではないかと現在推測している。父は状況を理解せず混乱して、決定にかかわることはできなかった。伯母に強く自身の意見を反対され、手術に同意した私の唯一の条件は腹腔内への転移をできる限り防ぐため必要な処置をとること、であった。手術を待っている私と伯母に伯母の同僚が話しかけてきた。『結局、どうなったの。』と。伯母は『ドレインを入れる手術を行うことに決めたの。』と答え、同僚は『そう。妥当な結論でしょうね。』と返事を返した。私たち家族が理解できない言葉で母の病状を世間話にする伯母を含めた看護師達に強い不快を感じた。その会話を傍らで聞きながら、何の根拠を以て妥当な結論と言えることができるのか、なぜその言葉の根拠を私に説明しないのかと強い反発心を感じた。しかしその気持ちを彼女達にぶつけることは得策ではないと自身の怒りを内に抑え込んだ。
外科の医師は肺がんと直腸癌との二重癌だと主張し、脳外科の医師達は直腸癌からの転移の結果の肺がんと主張していた。状況は混乱していた。しかしもはやどちらであったかを明らかにしたところで私達に何も得るものはない様に私には思われた。すべてが遅すぎた。5月から眼科、耳鼻科など関係の無い科ばかり受診して貴重な時間を浪費させていたのは誰なのか。なぜ私が頭に対しての不審を口にした時すぐにCTを以て確認してくれなかったのか。振り返ればそれよりも前、昨年末より『咳が出る。』と訴える母に感冒薬の処方を無為無策に繰り返していたのは外科の医師ではないか。その間にCTも胸の写真も撮られてはいなかった。伯母の『此処の病院に残せば、私の力で立派な先生たちに見てもらうことができる。』の主張の結果がこれであった。しかし伯母はそれに言及することはなく、もちろん私達への謝罪もなかった。振り返ればその時点で伯母の力にすがる方が賢明だと打算的に考えたのは私であった。この病院を選ぶことは母自身の決定であった。この状況について伯母を非難する権利の様なものは私達にはない様に思われた。この状況で私は何ができるのか、何をすべきなのか考えた。もう事態ここに至って転院はおそらく無理であろう。だとすればこの病院に最後まで責任を取って診療を続けさせること、究極の最後の時に必要があればこの病院にすがること。方法はそれしかないと私は思いつめた。
次の日私はデパートに足を運び、妥当以上の値段のウイスキーを買い求め、伯母からは副院長たる外科主治医医師の住所を手に入れた。ウイスキーに添付した手紙には、『懇切丁寧な先生の診療を受けていながら、今回のこの事態に対して本当に家族として申し訳なく思っております。このように事態になり至ってしまいましたが、患者は先生に診て頂くことを本当に嬉しく思っておりますので最後までお見捨てなきようにお願いいたします。』としたためた。住居を訪ねられた医師は私の顔を見て驚いた。ウイスキーを彼の手に渡し、『今後もお願いします。』と一言言って私は彼のもとを離れた。それ以上長く訪問すれば涙を以て激しく彼を詰問しそうであった。しかし彼を怒らせることは得策ではなかった。
ドレインを留置する母の手術は予定よりも長く時間がかかった。それは脳脊髄液を腹腔内に捨てることにより起きてくる腹腔内癌を何とか防いでほしい、との私の言葉によるためだと説明された。私は『ドレインのチューブを腹腔内でなく、体の外に出して癌が含まれているかもしれない水を体外に捨てることはできないのか。』と尋ねたのである。『その方策は取られなかったけれど、異例なこととして病理のドクターに脳脊髄液を検査してもらい、その中に癌があるかどうかを検査した上で陰性だったため、チューブを腹腔内に戻すことに決定した。』とのことであった。そしていよいよ肺への化学療法が始まることとなった。私は癌の化学療法がおこなわれる日を教えてほしいと希望したが、『不自然な行動をとることで患者に気が付かれるから。』と言う理由で却下された。数日に亘り癌の化学療法が行われたが、その時は激しい嘔吐に母は苦しんだ。氷を母の口に含ませ、嘔吐に汚れた口を洗いながらこの苦しい治療に今更どれほどの意味があるのか、強い疑問を感じたがそれを口に出して脳外科の主治医と喧嘩をすることも無用なことだと私は考えた。この頃母は脳外科の患者として入院していた。外科の主治医も信頼し脳外科の主治医も信頼し、自分の病気の本体も知らず、母はこの状況を治癒するものと信じていた。母の希望を何よりも大切なものとして、それを打ち砕くことを私は恐れていた。病気の本体のことを母はもちろん父にすら明かさなかった。伯母からは従妹の口を借りて『せめて、五味さんに説明するように。』とは伝えられたが、『伝えることで状況を好転させることができるのであればいくらでもするけれども、知ったところでどうしようもない事態なんだから父には伝えない。大事な人が日に日に弱っていく状況を何もできずに見つめていることほどつらいことはない、と思うの。父はその重みに耐えられない。』と拒否をした。そして誰に打ち明けることもできず、自分ひとりですべてを背負う覚悟をした。その重い苦しい日々に私の右頬が不自然にけいれんを始めた。一般的にチックと呼ばれる状況であった。私の心も悲鳴を上げていた。そのけいれんに気が付いたのは他でもない母であった。『みっちゃん、どうして右の頬がふるえているの。』『あらそう。気が付かなかったわ。』と答えながらやはり母は怖い、と思った。父はこの状況の中でとんでもないことを言い始めた。