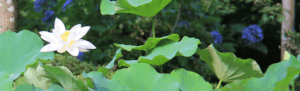肺への化学療法、それら一連の治療が終了したのは二ケ月後の9月初旬であった。
平成元年9月退院の前に主治医から母の病状についての説明があった。
しかし、その説明も父と私との新たな争いのもととなってしまった。父は一人で聞き、主治医の説明についての内容を私が尋ねると何も覚えていない、と語った。父の言葉に私は怒った。なぜ覚えていることもできずにその内容を家族に伝えることができないのであれば、どうして説明を聞くのかと。それに対して父は親を親とも思わない不遜な娘、自分の頭の良さを鼻にかけた娘と詰った。この頃の父と私はお互いを理解しようと努力せず、各自の行動、思考の穴を非難することに終始していた。命が尽きようとしている母親を放置し、喧嘩にあけくれ、お互いをなじりあう私達親子はたとえようもなく醜かった。
私はとりあえず主治医に再度の説明を求めた。現在の母の状況にどれだけの人生が残されているのかと説明をしてほしいと求めた。それに対する言葉は、転移性の脳腫瘍が化学療法の結果、落ち着いていて、肺がんだけの問題とだけとなれば、おそらく2年は生きられるであろうとのことであった。しかしその説明だけでは納得できなかった私はさらに主治医に尋ねた。脳腫瘍が止まっていないとき、余命はいかほどと推測できるのか、と。その場合おそらく来年の正月を迎えることは無理であろうと、彼は答えた。すでに9月中旬、正月までには三ヶ月余りしかなかった。2年なのか、三ヶ月なのかはっきりさせてほしい、と私は要望した。二年であれば看護を長期戦とみなすし、医療費としてかかる金銭、私達自身の生活費の問題もある。私の収入が私達家庭の唯一の収入となっている時に自身の仕事をこの時点で止めるわけにはいかなかった。しかし三ヶ月であればすべてのことよりも母親のことを最優先したい、仕事を中止しすべてのエネルギーを母の看護に注ぎたかった。一体三ヶ月なのか二年なのか、そこのところをどちらなのかはっきりしてほしいと、医師にさらなる説明を求めた。しかし医師は、『どちらなのかわからない。』と繰り返すのみであった。
余命に対して診断が確定しないままに自宅療養が始まることとなった。
現在とは異なり制度も何もない時代であった。母親のために1階の続き間の和室を寝室にし、必要なものをすべてそこに移した。和室の畳の上に直接布団を敷きその上に母は臥床していたが、すぐに立ち上がるためにベッドが必要となった。家具店に行き、店頭に陳列されている商品の中からとりあえず購入可能なベッドを早急に入れてもらうこととした。しかしベッドからでさえ起き上がることがすぐにできなくなっていった。排泄はベッド上に寝かせたままで行わなければならなくなった。その状況に私もベッドの横に寝ることとした。母親の手首と自分の手首を腰ひもで結び、母親の動きを察知し、自分がすぐに対処できるように態勢を整えた。退院直後はまだ普段と同じように暮らしていた母であったが、観察をしていると日々できないことが増えていくように思われた。二階に上がる階段を上る事ができなくなっていく、短い散歩に出て痙攣様の発作を起こし、そのまま散歩に出ることを怖がるようになった。お地蔵様に毎日お参りをし、『美智子とお父ちゃんがいつまでも元気でありますように。』と手を合わせることができたのはいつまでだったのか。畳から立ち上がれなくなる、ベッドから立ち上がることすら不可能になる。時が静かに流れる中に辛くて悲しい日も希望の灯がともるうれしい日もあったが、辛い日のみが次第に多くなっていった。状況は私にただならぬものであると告げていたが、2年なのか三ヶ月なのか見極めようと私はあがいていた。
今当時の事を思い起こしてみると、脳腫瘍は明らかに進行していたのに、私の気持ちはそのことを認めることを強く拒否していたのだろう。この頃もはや病院に母親を連れていくことは意味のない、不可能な事ことであった。母を自宅に残し、私は一人で毎月脳外科と外科の受診を続けた。そして母の状況を報告し続けた。それは医師達に対しての私の意地であった。彼らの行ったこと、彼らのなしたことの結果を、そして私の運命すら変えてしまうことになった、彼らの診療の結果を見極めて欲しい、と思っていた。昨年の段階で母が継続的に咳を訴えた時点でなぜに胸のCTが撮られなかったのか、せめて胸の写真の一枚でも。それが一番の私の疑問であった。この時点で肺への転移が発見されていれば、結果は幾許かでも変わっていただろうか。結果論に過ぎなかった。でも私達は少なくとも納得をすることはできた。しかし現実は関係の無い科の受診を繰り返し、脳転移まで招いてしまった。脳転移が確定されるまでどれほどの無駄な時間を私達は過ごしたのか。訳が分からず苦しむ母の状況を叔母に相談しても、主治医との私達の会話の仕方が悪いと非難された。そして主治医の最後の言葉が『もううるさいから眠らせておけ。』と言う言葉であった。一連の彼らの対応がどれほど私達家族を混乱の中に落とし込んだのか、最終的に私達家族をどれだけ悲嘆に突き落としたのか、最後まで医師に見定めさせたいと言うのが私の思いであった。その思いを淡々と胸の中に抱えて、主治医との面談を私は続けた。