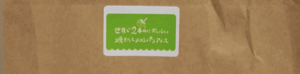その頃、私は母に対する見舞いをほとんど断っていた。
もはや焦点の定まらない動かない眼球、頭髪を失った頭、頭皮すぐ下に見える腹腔内流れ落ちているドレインのチューブ、そして何よりも母の訴える強い倦怠感。母を知る人には元気で、活発で頭脳が明晰であった母の姿のみを覚えていて欲しかった。病み衰えて姿の変わった母の姿、自身の状況に戸惑い、悩み、自信を無くして縋る母を見て欲しくはなかった。その私の思いから父の兄弟ですら『今母が休んでいるから。漸く眠ったところであるから。』との理由で追い返した。叔父たちは『お前は俺たちから何か隠している。何かあるのならば知らせてもらわなければ困る。』と苦情を述べたが、私は『なにもありません。』としらを切りとおした。『彼らは何のために会おうとしているのか。患者を見舞う目的は何なのだろうか。励ますために、病気に勝つために、でもそれはもうあり得ない。では一体何のために。自身が母と別れを告げるため。でも母の命が明日にも終わろうとしていること、それは私しか知らない。母自身もまだ治ると思っている。』
そんな日の中で母の友人が母を見舞いに訪ねてきたことがあった。もともと私達の以前の自宅の近くに住んでいた人であった。でも親類以上に親しい付き合いをし、旅行も一緒にしたことがあった。その後関東の方に引っ越しされたが、母の状況をその方と絶えず電話連絡しながら伝えていた。その方が少しでも元気なうちにと関東から見舞いに来られた。私達とは親しい付き合いをしておられた方であったし、私のその時の動きも知っておられたし、両親お互いの親類の難しさもわかっておられたので、母に会っていただいた。その方に母は『美智子は本当によくやってくれる。私は自身の親を美智子ほども面倒を見なかった。でも本当にあの子がいてくれて支えられている。でもあの子が病気になった時に一体誰が助けてくれるのだろう。私はあの子の幸せを考えて結婚させずにこれまで生きさせてきた。でも私はとんでもない失敗してしまったのかもしれない。あの子が一人で将来病んだ時のことを考えると私は死にきれない。』
この言葉はいつまでも私の心に残った。母が死にきれない、と口にしたのは自身の病気を認識し、余命が限られていた事を意識していたわけではないと私は考えている。おそらく一般的な親が先立つという考えに基づき、口にした言葉であろうと私は考えている。それよりも興味深いのは母が私の人生に対して介入して、自分の判断に基づきコントロールしていた、と言う事を認めた点であった。母が死亡した時私は33歳であったが、それまで男性と交際したことも、デートのようなことをしたことも全くなかった。『あなたは美人ではないのだからしっかりお勉強して、自分で自活してゆくことを考えなさい。』口酸っぱく母が私に説き聞かせた言葉がそれであった。母と私は全く同じ顔をしているにもかかわらず。顔だけではなく、声も身長も私達二人はほぼ同じであった。血液型まで。知らない人が見れば二人の人間がいると見分けることができなかった。母の故郷の人も私の顔を見るだけで母の子供だと分かった、と言う。電話で受け答えをしても父でさえ母と話しているのか、私と話しているのかの区別がつけられなかった。唯一母の父、私から言えば祖父だけが聞き分けていた。しかしそれも声ではなく、『美愛子が電話に出れば毎度おおきに、と口にするが美智子が電話に出ればこんにちわ、としか言わないだろう。それで以て見分けがつくよ。』と言うありさまであった。
母の母、祖母は非常に美しい人であった。和歌山市で祖父と出会い結婚したが、祖父は自身から逃げることを恐れ、子供ができるまで祖母に金銭を持たせることはなかった、と言う。祖父は祖母を大切に生涯の恋人として扱った。その祖母に似て叔母たちも美しかった。父は時折『自分は一番のかすを押し付けられた。』と冗談交じりに口にした。おば達からも『美智子は不細工な子。』と言われて私は育った。幼い時からその環境で育った私は頭脳で勝負をしなければならないのだと、そして自分の家は貧しいのだからまして頑張らなければならないのだと思い込まされていた。私の衣服や髪型を母は自身がなくなる時まで、徹底的に自身の思い通りにした。おしゃれな洋服は絶対に選ばせてはくれなかった。髪型も宝塚の男性役の様に短く刈り込んでいた。美容院の後ろの待合の席に座り、美容師に細かく指示をし、魅力的とは程遠い女学生の様な非常に硬いスタイルを作らせた。選ぶスカートもひざの中までのひざスカートばかりであった。その選定も母の好みだった。私自身でおしゃれなスカートをデパートで選んで購入して帰ったとしても母同行の上で返品交換に行かされた。
その一方で、土地の購入や大工の方々との交渉の席には同席をさせた。今よりも個人情報の甘い時代、郵便局、銀行に預金の預け入れ、引き出しに行かされるのも私の仕事であった。私が大学に進学した時『たった一人のお嬢さん遠い金沢に行かせるのは寂しくないですか。恋人ができたらどうします。』の言葉に母は『私はあの子をそんな娘に育てておりません。』と自信をもって口にした。金沢大学卒業後、学習塾で経営に成功すると母の自信はますます強くなった。私の成功は自身の薫陶の賜物と母は考えた。『これだけの収入があって、これだけの財産があるのに結婚なぞばかばかしいわよね。』と口にした。母は私とともに事業を大きくしていくつもりだった。父は努力家ではあったが、細心な人であった。母は人生全般に対して野心家であった。私を通して自分が本当に生きたかった挑戦に満ちた人生を母は生きようとしていたのではないか、と私は深く疑っている。それが母自身の希望から出たものなのか、それともそうすることが私自身の幸せな人生なると考えていたのか、答えは未だに見いだせない。
私が幾度か母にとって危険な行動をとろうとしていることを母は意識したことがあったと思う。その折に母は問題に直接触れずに巧みに対処した。特に金沢大学の1学年上の方に淡い恋心を抱いたことがあり、卒業の翌年再三にわたり私は金沢に行こうとした。スキー旅行の話も出ており、参加するつもりであった。しかし母は『学習塾を開いてまだ軌道に乗らないときに受験前の大事な時期に塾長が遊びに行くのはどうなの。』と言って私に考えを翻すように迫ってきた。好きな人がいるらしいことには何も触れてこなかった。反論の余地はなかった。母のいうとおりであると私自身理解できたから。それが母のやり方であった。理詰めの正攻法で私を責めてきた。いつも母は正論を唱えた、そしてそれに私は勝てなかった。万が一それに逆らうと結果として負けるのはいつも私であった。若い私には母と太刀打ちできなかった。自身で何かをしようとすると状況は複雑になってきた。入り組んだ事態を打開するためには最終的に母の力を借りるほかなく、母は知恵を貸してはくれたが、徹底的に私の誤りを指摘した。そうしたことを繰り返していくうちに、母の言うとおりに振舞っている方がはるかに楽だと私自身も母の指示に従うことに慣れていくことになった。きっとこの時の母の言葉はそうしたいくつかの私との葛藤を振り返って、私が自分自身で歩くのを妨げたことに対して吐かれたものであっただろう。『今時、親の面倒を見る子などいないわよ。私が子供作ったとして、私が病気の時に助けてくれるかどうか。そんな都合の良い話なんかないわよ。』とその場で母の言葉を打ち消した。母の終末を機縁として私自身の人生の在り方も大きな転換期を迎えていた。しかしこの時点で私はまだそのことに気づいてはいなかった。
平成元年12月28日容体は一段と悪化した。
自身の弟すら認識できない状況であった。それほどに脳は破壊されていた。しかし父と私は認識できた。『お父ちゃん、美智子。おしっこが出たと思う。おしもを変えて。』と母は訴え、対応を求めて私達は救急車で母を病院に運んだけれども、もはや何もできることはないとのことであった。父の親類も母の親類も集まった状況で私を除く他の人々は母をこのまま入院させた方がいいと意見を述べた。しかし私は一人で自宅に連れ帰ることを強く主張した。病院に入院したところでもはやこの状況ではベッドにただ寝ているだけ。治療も何もすべはない。加えて正月の病院の寂しさは言い尽くせないものがある。帰宅、外泊することが可能な人は帰り、スタッフも正月休みのために最小限となるであろう。今回の正月は母にとっておそらくこの世で最後のものとなるであろう。せめて一口でも雑煮を食べさせてあげたい。最後の正月を普通に自宅で送らせてあげたい。私の思いであった。
入院させる方がいいという親類たち、連れて帰ると主張する私『面倒を見るのは私なのだから。』と。どちらも一歩も引かない状況に脳外科の主治医は困り果てた。『本人さんに決めてもらいましょう。』主治医はこう言って争いをとりあえず収めた。『五味さん、しんどかったら入院してもいいよ。部屋も用意してあるし。でも自宅に帰りたかったら帰ってもいいよ。どちらでも君の好きなほうでいいよ。どうする?』と主治医は母に尋ねた。母は『自宅に帰る。』と迷うことなく答えた。それを聞いて主治医は『分かった。準備するね。』と言って母の傍らを離れた。すぐに私を少し離れた廊下の曲がり角に手招きで呼び寄せた。彼は私に『君は怖くないのか。お母さんは死ぬよ。実質一人で看取りができるのか。』と尋ねた。『でも先生、母の運命は決まっているでしょう。私が自宅で看取ることを選んだところで不自然に母の命を短くすることはないのでしょう。』と私は答えた。
その日のうちにタクシーに乗せて母を自宅に連れ帰り、闘病生活、看護生活は再び始まった。12月31日、私はお正月の用意をするために一人で郊外のショッピングセンターに出かけた。ショッピングセンターでは正月の童謡歌が流れ、値段札も含めて店内の装飾は正月気分一杯であった。幸せそうな人で溢れていた。親子連れ、夫婦のカップル、どの家族もにこにこと幸せそうな顔をしていた。昨年は父の入院のために母と私の二人であったが、その前の年までは家族三人でいつもこのショッピングセンターを訪れていた。自宅の掃除、私の仕事場の掃除、車の洗浄等、正月を迎えるためのさまざまの準備が終わった後、家族揃ってこのショッピングセンターを訪れるのが常であった。その時は私達の心も新年を迎える準備に浮かれていた。もうあの楽しかった時は永遠に戻ることはない。父は妻を失い、私は母を失い、これからは今年のこの辛い年末の思い出とともに正月を迎えることとなるであろう。私達がこれほどに辛い思いを抱えているにもかかわらず、周りの情景の変わりのないのが不思議であった。どうして私達はこれほどに苦しいのに、町の情景は何も変わりがないのであろう。一人社会から浮き上がったような不思議な感覚を味わいながら、必要なものを急いで買い整えるとショッピングセンターをあとにした。大晦日、母から教えられたように丸いものは丸いままに来年一年が丸く物事すべてうまく行きますようにとの願いを込めて雑煮のための野菜を切りそろえた。金時人参、青首大根、里芋、油揚げ、そして丸餅。そして元日いつものように雑煮を調理した。入れる材料に違いはないけれど、味わう心は今までの年とは異なり悲しみが一杯で、涙をこらえるのが難しかった。今年がいかなる年になるか、それは分かっていた。でもそれを誰とも共感できないことが一層私の心を辛くした。母は私が調理した雑煮に対し、『野菜の切り方はへたくそだけれど、味はまあまあだわ。』と笑い、一口、二口すすった。1月ゆっくりと一日、一日が経って行った。