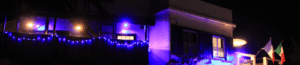翌朝から二間続きの和室に鯨幕を張る作業が始まった。
単に張るだけでなく時にドレープ、天蓋状と装飾を込めて悲しくも美しく張られていった。
その様子を叔母たちは見つめながら『私の時はピンクがいいわね。私は紫の方がいいわね。』などと口にして騒いでいた。その様子は自身の妹、姉の葬儀ではなく、何か楽しい宴会の準備でもしているかの様に思われた。昼が近づいてくると、叔母たちは昼食を要求してきた。夕になると夕食を。そして次の日も勿論。通夜の折の簡単なつまむものと葬儀後の精進上げは予想していたがそれ以外に伯母たちに食事を用意せねばならないことを知らなかった私は大急ぎで精進上げを注文していた料理屋へ軽食の手配を依頼した。
カバンに大枚の現金を入れて、そこからの現金を手に、様々の手配に走り回っていた。打ち合わせの時に来た葬儀社の番頭の方は『休んでいた方がいいですよ。顔色が悪いですよ。』と口にするけれども、休めるような状況ではなかった。焼香順序の決定、折り合いの微妙な父方の親類と母方の親類の関係、それを理解しているのは私であり、最悪苦情を言う親類がいたとしても、母の希望であった、と一言で押し切るつもりであった。次々に届く生花、それをどういう順番で飾るか、母を立派に見送らなければと言う気持ちと自身としてはどうでも良いとしか理解できない雑事に心煩わせなければならない事が不本意だった。そこに叔母たちとのやり取りが混じって余計に私を疲弊させていく。『もう、いや!投げ出したい。』と心の中で叫んでいるけれど、それをすれば恥をかくのは私ではなく、母なのだと思い返す。私が立派に葬儀を締めくくることが母の最期の花道を彩ることとなるのだと思い直して、心傷める雑事に一つ一つ取り組んでいく。
その中でいずこともいわず外出していた父が突然帰宅してきた。そして『 『体がしんどいから病院に行ってきたが、奥さんのことが済んだら入院した方がいいですよ。』と言われた。』と言って布団をかぶって二階で寝てしまった。『昨日からさっきまで打ち合わせができたのに今できない筈はないじゃない。それほどに体が悪い筈があるわけではないじゃない。すべてを放り出せる状況でないのはわかっているはずなのに。』父の無責任に腹が立った私はそのまま父の所に行き、布団を引きはがして『ちゃんと最後までできないのであれば喪主を降りて。』と迫った。しかし、父を翻意させることはできず、もとより今更喪主を変更することなど挨拶状のことを考えれば不可能であった。とうとう父は通夜の間布団に臥床して終わった。一度も通夜の会葬者の前に姿を見せることはなかった。
翌日は葬儀であった。私が教えていた生徒の父兄、取引先の銀行関係者、親族姻族、含めてかなり盛大なものとなった。父は葬儀の時には布団から出てきた。私達の自宅は交通量の多い道から分岐し50mほど住宅街に入ったところにあった。焼香して下さる人に向かって座るのは私一人で十分と叔母たちは前日に語っていた。もう彼女達に何も反論する気持ちはなかった。叔母たちが行って来た事、そして行っている事はすべて世間の人たちの目にさらされている。近隣の人々は母と親しく会話していたから、祖母死後の母の行き場のなかった悲しい思いを打ち明けられていた。母の実家の仏壇が私たちの家にあった理由も知っていた。母が病院から自宅に帰って時、とるものもとりあえず私達に悔みを述べるために自宅に来てくださった人はそこに仏壇がないことに気が付いていた。でも私も何も語らず、彼らも何も問わなかった。何かを口にするには余りにも私は疲れすぎていたし、正常な判断ができるとも思えなかった。『もう何でも良いから勝手にしてくれ。』と言うのが私の本音であった。焼香に来てくださった方にお顔を拝見し頭を下げて礼をし、焼香を終わって頂いてまた頭を下げる私に、叔母は『礼はどちらか一回でいいの。』と指導してきた。来てくださった事に対してのお礼、焼香して下さった事へのお礼、二回のお礼は意味が異なる、と私は考えていた。叔母たちに従順でない姪は『自分達だって大した事は知らないくせに。』と心の中でつぶやき、やり方を変えようとはしなかった。それがますます叔母たちの怒りを招くことになるだろうことは理解していたけれど。読経料、戒名料等々いかがしたのか記憶には残っていない。当時の住職の方がすべからく計らって下さったのだと思う。しかしこの後何年にも亘って住職の方は『お父上が倒れられて、あの時はどうなるのか、と思いましたよね。』とたびたび私に口にした。在所の方々の様々の事を見聞きし、保護司まで務められたご住職の方を戸惑わせるほどの異常な状況だったのだと振り返る時、30歳そこそこだった私がよくこの状況を乗り切れたものだと感慨を深くする。そこにはご住職の方の目立たない助け、葬儀社の方々の支援があったことは言うまでもない事である。
火葬の旅立ちのために家を出ると道には私の要望の通りタクシーが控えていた。これは生前の母の希望であった。母は生前、タクシーの長い車列の葬儀を見ると、よく『見て、見て。見事な葬儀ね。』と口にした。それに対していつも私は『確かにね。でも私も一人っ子で結婚もしていないのに、うちがあんなことをしたら誰がタクシーに乗るの。ほとんどの車が空で走ることになるのよ。』と返していた。でもいつもこの会話が繰り返されるにも関わらず、母は私の注意を引くことをやめようとはしなかった。幾度となく繰り返されていたこの会話が私の心の中に残っていた。たとえ空で走ることになってもいい、母の希望をかなえてやる、と言うのが私の決意であった。母の霊柩車が家を離れる時、家から広い通りに出る角の所に葬儀社から数人の人間が出て、タイミングを計り,にぎやかな道の車を一時止めて霊柩車に引き続いてタクシー10台が円滑に隊列を乱されないように引き続いていくように手配されているのを確認した時、母の最期の望みが滞りなく叶えられたことを私は感じた。母の人生最期の花道であった。私はタクシーの中で母のために自分が行おうとしたことが円滑に流れていることを確認し、一応満足することが出来た。しかし次の瞬間、何を引き続いて行わなければならないのか、を考えていた。全く涙を流す暇はなく、私がきちんと執り行うことが出来なければ、母の顔に泥を塗ってしまうことになるのだとばかり考えていた。しかしそれと同時に気になったのは『父が早急に入院しなければならないだろう。』と言ったという医師の言葉であった。それは一体どういう意味なのだろうか。この問題を解かなければならない、タクシーの中で私は考えていた。この時、次なる難問が控えていることになろうとは全く予想していなかった。