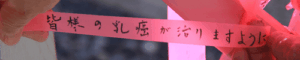成人式のあくる日の16日、母の容体は再び変化した。
今回は尿が出なくなった。私は状況を叔母に電話で伝えた。伯母は病院に運ぶように私に指示してきた。
伯母の指示の通り救急車を呼び母とともに病院に向かいながら、もうこの道を母は生きて戻ることはないのだと考えた。とうとうこの日が来てしまった。病院に着くと母はすぐに個室に収容された。ドクターたちが次々と母を訪れながらももはや何もすることはなかった。私達の看護の行き届かなかった体にたまった垢を看護師が落としてくれるぐらいであった。
検査も必要なく、薬も必要なく、ほとんど眠り続け時折思いついたかの様に目を覚まし、その時だけ少し意識が覚醒するように思われた。しかし近親者のほとんどを認識できないことは同様であった。唯一の救いは脳細胞があまりに腫瘍の侵襲を受けていたがために肺がんの進行の伴う苦痛を訴えないことであった。
自宅療養中ほとんどの見舞客を断っていた私であったが、叔母はその方針を改めるように私に迫ってきた。
特に叔母の夫の姉妹の見舞い訪問を受け入れるように求めた。進行しつつある状況を不用意な言葉で母に悟らせることを恐れて見舞客を断ってきた私であるが、もはや彼らが涙をこぼそうと、ベッドサイドで泣きわめこうと母がそれを認識することはできない。私は叔母の頼みを受け入れた。
しかし、この状況に彼らを招き入れることにどれほどの意味があるのかと尋ねたい気持ちは胸の中にくすぶってはいた。病室の入り口で変わり果てた母の姿を見た彼女達は硬直して『かわいそう。』と言って泣いた。かわいそう、その言葉を聞きながら、それは上の位置にいる人間からの下位の人間への憐みではないだろうかと、感じたのは私の僻みであろうか。
病に倒れた母の姿を通して彼ら自身の幸せを確認しているように感じられて私は嫌悪を感じた。
私は自身の仕事の中で受験前の中学三年生のみを残して残りの学年の授業をすべてやめることを生徒、及び父兄に告げた。
母の最期の看病に最善を尽くしたい、少しでも長い時間をその傍らにいたいという気持ちからであった。その時間のみ自宅に帰り、後は個室寝泊りをすることを自分に課した。この頃父は体が辛いと言い短い時間母を見舞った後ほとんど自宅で休養することを習慣としていた。私は母の病室に行かないときには知人を通して葬儀社との接点をつなぐこと、父に掛けられていた保険の見直し、母の墓所の購入を計画し、と空いた時間には走り回っていた。そのどれもが母の死を確定したこととして動き回っていた。
そうした活動を行っている自分自身に嫌悪感が湧いてくることを止めることができなかった。箪笥をかき回し、祖母から母に贈られた大島紬及び自分が母の日に購入した仕付け糸のままの長襦袢を見つけ出し風呂敷包に固く包み、母の死装束として私の車に積み込んだ。母の死装束を用意している自身に立腹する日々であった。自宅から母の病院に向かう途中に小さな橋を渡らねばならなかった。その橋を渡るたびに橋の欄干より母の死装束を川に投げ込みたいと感じた。でもできなかった。当たり前である。それが必要になることはもはや変えることができない母の運命だから。でも変えることのできない運命としてあきらめている自分自身が腹立たしかった。どうして死装束を投げ捨てて母の回復を祈れないのか、どうして最後の最後まで奇跡を信じることができないのか。それのできない自分を情けなく感じた。母のための紙おむつを毎日必要最低限しか買わないことも、情けなかった。
でも母は着実に死に近づいて行っていた。眠る母のそばで夜も本を読みながら、そして母の気配を全身で観察しながら、母が着実に弱っていくのをなすすべなく眺めていた。この人により私の人生は計画され、制御され、その人の思い、期待を実行することを期待されていった。そこに私への愛情がどれほどにあったのか、あるいは自身の人生を全うしようとする母自身の我欲だったのか。それでも楽しい日々であった。母の私への強い愛情は感じていた。それゆえに母が私の人生を強く制御することも許してきた。そうして紡がれた思い出のいくつかが私の心を駆け回っていった。
そんなときに叔母は『一軒の家に苗字の違う二軒の家の仏壇があることはまずいことだから、万が一の時にはお祖母ちゃんの仏壇をあなたの家の二階に移させて欲しい。』と頼んできた。それを当然のこととして同意しながらもこの時期にそんなことを私に言ってくる叔母に情のなさを感じていた。しかしこの人にそれを求めてもこの人の常識と私の常識とは違うものだから、と自身を納得させた。そしてとうとう2月19日午後7時10分、母は息を引き取った。伯母はかねてから頼んできたとおりに、仏壇を動かしたいから家の鍵を貸して欲しい、と私に頼んできた。それは父に言うべきではないか、長年の世話に対し父に礼を述べるべきではないか、と瞬間思ったが、もはやこの期に騒動は避けたいとの気持ちが強かった。
問題の死装束を看護婦たちの手で着せられ、寝台車の用意がなされ、私達が母とともに病院を離れたのは叔母たちよりかなり遅かった。私達が家に帰った時、祖母の仏壇は私達の家から消えていた。もしやと思い、向かいに立つ私の家にも急いだが、その二階にもなかった。私は心の中でやはりとつぶやきながら、嘘をついた叔母にますます信頼できないものを感じていた。仏壇が消えている事、自分の知らないままに自分の家から持ち出されたことについて父は何も口にしなかった。